不登校になった子ども。
教室には行きたくないって言う。
教室に行けないなら家で過ごすしかないのかしら?
家族以外と交流がなかったり、留守番ばかりさせるのも心配ですよね。
今回は小学生や中学生で不登校になった子が過ごせる居場所を紹介したいと思います。
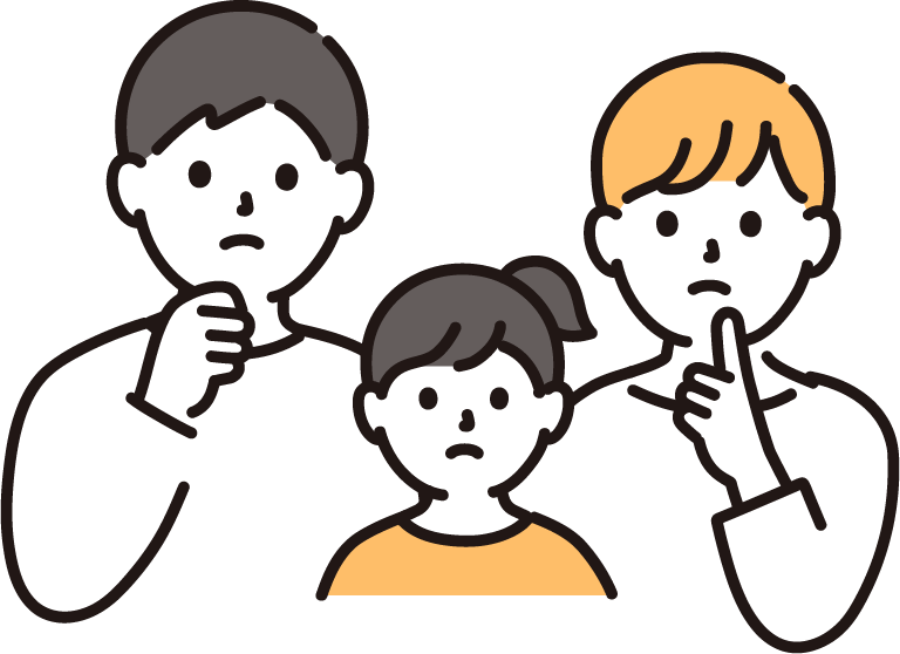
校内教育支援センター
小学校や中学校には教室だけでなく不登校の子や行きしぶりのある子が教室ではない場所で過ごせる居場所を作っている学校も最近では増えてきました。
昔は保健室くらいしか居場所がなかった子も、教室でも保健室でもない場所で少人数で息抜きできることで足を運べる子も居ます。
校内フリースクールとか相談室など呼び方は学校によって違います。安心・安全な場所を提供できるよう運用されています。
在籍校はどこに配置されていて、どんな雰囲気なのか確認してみてください。

適応指導教室
教育支援センターと呼ぶところもあります。自治体が運営しており、在籍校と連携されているため料金も基本的に無料です。
元の学校には在籍していて、自治体が運営している場所に自分のペースで通う形になります。出席扱いになるかどうかは判断が異なる場合があるので在籍校に確認してみると良いですよ。
外で遊ぶ時間があったり行事をしたり。活動内容も様々です。
相談業務や訪問支援をしているところもあります。
学びの多様化学校
以前は不登校特例校と呼ばれていましたが2023年8月より学びの多様化学校に名称が変更されました。
法律で認められた学校なので、通常の学校と同じように卒業して進学もできます。
公立と私立があるため学費はそれぞれ異なりますし、学校によって特色も異なります。

学びの多様化学校はその名の通り、一人ひとりに合わせた授業カリキュラムだったり、支援体制が整っていて不登校の生徒に配慮されています。年間の総授業時間数が少ないことも特徴にあります。
令和5年では全国で21校とありましたが令和7年では57校と徐々に増加しています。
しかし、全国的にまだ少ないのが現状です。
国は、将来的にはさらに設置を増やすことを以下のように目指しています。お住まいの地域に設置されていないこともまだありますので、今後誰もが転居したり遠方に通学しなくても自由に選択できるようになるといいですね。
不登校児童生徒を受け入れる不登校特例校については、令和5年3月現在、全国で 21 校の設置に留まっているが、文部科学省では今後早期に全ての都道府県・政令指定都市に設置されることを目指すとともに、将来的には希望する児童生徒が居住地によらず通えるよう、分教室型も含め全国 300 校の設置がなされることを目指しており、各設置者においても、分教室型を含めた設置に向けた取組が期待されること
文部科学省
夜間中学
夜間中学も学び直す場として徐々に数が増えている場所です。まだ各都道府県にはありませんが、令和6年10月時点で53校、令和7年にも新たに設置されていく予定です。
朝起きるのが辛い起立性調整障害があるお子さんも時間をずらして学ぶことができます。
夜間中学は夕方から始まって夜21時頃まで勉強するスタイルです。以前は戦後の混乱期で仕事などで学習することができなかった人が対象でしたが、今ではそれだけではなく外国籍のお子さんや不登校でほとんど学校に通えなかったお子さんも利用しています。

夜間中学に入学するには学びの多様化学校と同様に設置数が少ないためお住まいの近くにはないという場合もあります。
希望するには夜間中学や教育委員会に問い合わせることが必要です。
入学希望者のうち夜間中学への入学を認められる方は、基本的には、不登校や親による虐待等により中学校等の課程の大部分を欠席していた方を想定していますが、様々なケースが考えられるため、入学の許可に際しては、出席日数等の一律の外形的な基準によって決定するのではなく、個々の事情に応じて柔軟に判断することが望まれます。
文部科学省
色々な年代の方や外国籍のお子さんもいらっしゃるので多様化を肌で感じることができそうですね。
フリースクール
個人やNPO法人、民間企業など運営は様々な形があります。
通信制高校やサポート校が中等部フリースクールを運営している場合もあります。
目的も学校へ復帰を目指す場所や、他者との交流を目的としたり、家以外の居場所を作る場所、勉強以外の体験を通じてエネルギーを蓄える場所、日常生活の力を得る場所など多種多様です。

ホームページやインスタグラムなどの情報で確認するだけでなく、実際に足を運んでみてみることが大切です。
何よりも本人が居心地が良いか。体験プランも用意されている場所もあるので問い合わせてみましょう。
通うことで出席扱いになるかどうかは、在籍校に確認してみましょう。
民間施設における指導等に関して「出席扱い」が考慮される場合には,当該民間施設における指導等が適切であるかどうか,学校長と教育委員会が連携して判断することとされています。
文部科学省
料金もそれぞれ異なるため、料金も踏まえて色々と比較検討することが必要です。
東京都、愛知県、三重県などの一部の自治体では補助金の制度が始まっているので、これからどんどん全国に広がっていくと良いですね。
放課後デイサービス
こちらは特性があるお子さんが対象です。
平成24年に児童福祉法の支援によって放課後デイサービスが創設されました。
利用するには医師からの診断書や受給者証が必要になります。
学校に籍があれば不登校でも利用できます。
学校に行けないときも放課後デイサービスなら行けるという場合があります。
家族以外の第三者と交流があるこで居場所となったり、身体を動かすことで生活習慣を取り戻すことができます。
ゲームや料理、習字や作品づくりなどを通じて、達成感を味わうことで自己肯定感を高めるなど成長を促すことができることもメリットです。
事業所によりスタッフの人数も異なります。それによって1日の受け入れ人数が違う場合があります。
日常生活の活動に力を入れている、体幹の訓練に力を入れている、日々の行事を通して仲間とのつながりを大切にするなど事業所により雰囲気が異なったり、力を入れている部分が違います。
放課後デイサービスを決める際には相談員支援員さんから詳しく情報収集したり、事前に見学をすることが大切です。
学習塾や家庭教師
子どもにとって居心地が良いのであれば学習塾も居場所となるでしょう。
集団で授業を受ける塾だけでなく、個別塾やオンラインを活用しながら自分のペースで進める塾もあります。
通学するのが億劫な場合は家庭教師やオンラインの塾もあります。
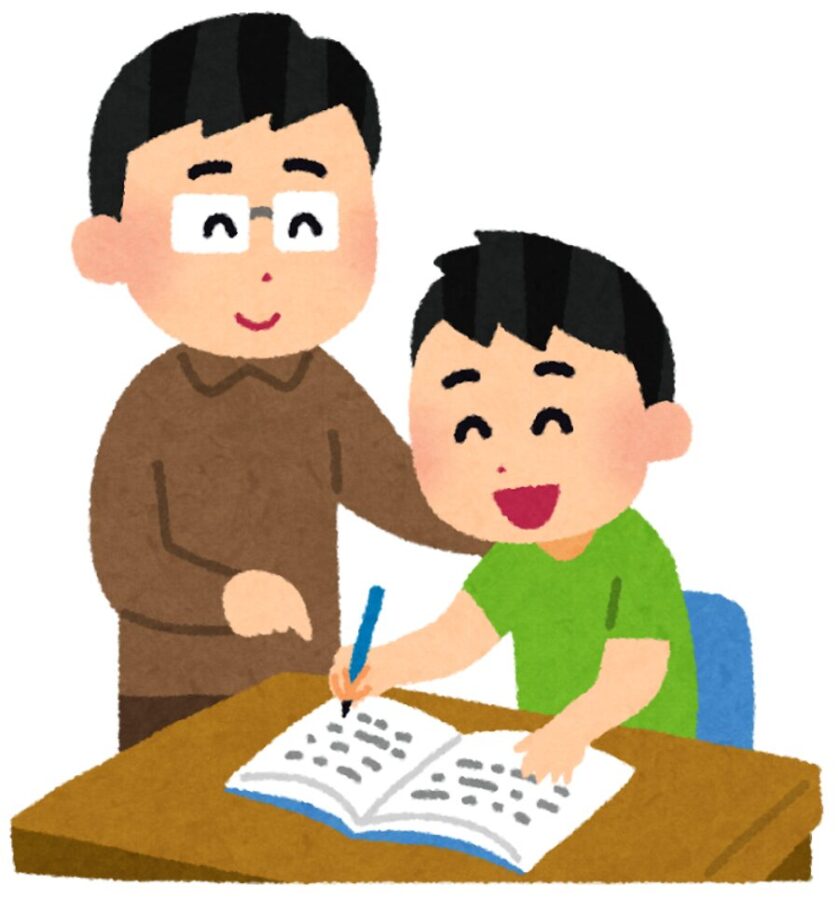
休み時間がなく勉強することに主軸を置いた空間は、集団でざわざわしたところが苦手な子にとっては安心できるスペースになる場合もあります。
特性に合わせた学習支援をしている塾もあります。
家庭教師では経験豊かな講師がいるところや大学生など若い先生が指導してくれるところもあります。
相談しやすい、話しやすい講師であったことで学習に取り組みやすくなることもあります。
お子さんにあった塾を選択することが大切です。
番外編
居場所がどうしても見つからない。何より本人が嫌がる。
家ばかりにいるのもどうしても外せない用事もあるし困った!
そんなときのために番外編としてその他の場所を提案したいと思います。
すべての人にぴったりではないけれど外に出る機会になれば幸いです。
祖父母
家ばかりでちょっと違う人ともお話しして欲しい…
そんな時、祖父母に頼める人は手伝ってもらいましょう。
祖父母が近くに住んでいて、理解があること。孫とも仲が良好であることが必要です。
一緒に花を育てたり、将棋を教えてもらったり。
親が教えるのとまた違うことを知れる居場所になります。
気分転換の場所として、市の行事や近くの公共施設で行われているイベントに参加する方法もあります。
随時参加で、親が送迎したり、イベントによっては一緒に参加する必要があります。
親の時間の都合をつける必要はありますが、子供の興味のあることについて深めることができます。
公共施設や民間企業の体験イベント
家では体験できないような知識の豊富な講師から生き物について学んだり、工作をしたり。
民間企業が工場見学や体験教室を開いている場合もあります。
子どもの好きが見つかる機会になるかもしれません。
ファミリーサポート
急な用事があるときなどは、小学生6年生までのお子さんの場合はファミリーサポートにお願いする方法もあります。
お母さんがたまに息抜きしたり、利用することで結果的に第三者とお子さんが交流する機会が得られます。
お住まいの市町村によって利用方法や条件など異なる場合もあるため確認してくださいね。
初めて利用する時は、人見知りのお子さんや初めての人が苦手なお子さんもいるので事前に相談したり事前に面会してみるのがいいでしょう。
家事代行
夕食作りなどの家事を代行してもらいお母さんが時間を捻出する方法もあります。
意外と時間の掛かる家事をお願いすることでお母さんの負担が軽くなります。
お母さんに余裕ができればゆとりのあるコミュニケーションができるようになります。

ワーキングママの場合はお子さんが不登校になることで、仕事が続けられるのか、辞めないといけないのか、勤務時間を短縮するのかと悩むこともあるかと思います。
それはお子さんの年齢や状態、きょうだいの有無、家計の状況などは人それぞれのため答えは同じではありません。
お子さんの状態によっては外出することが難しい場合もあります。お子さんとも相談しながら親子ともに居心地の良い場所を作っていけるといいですね。
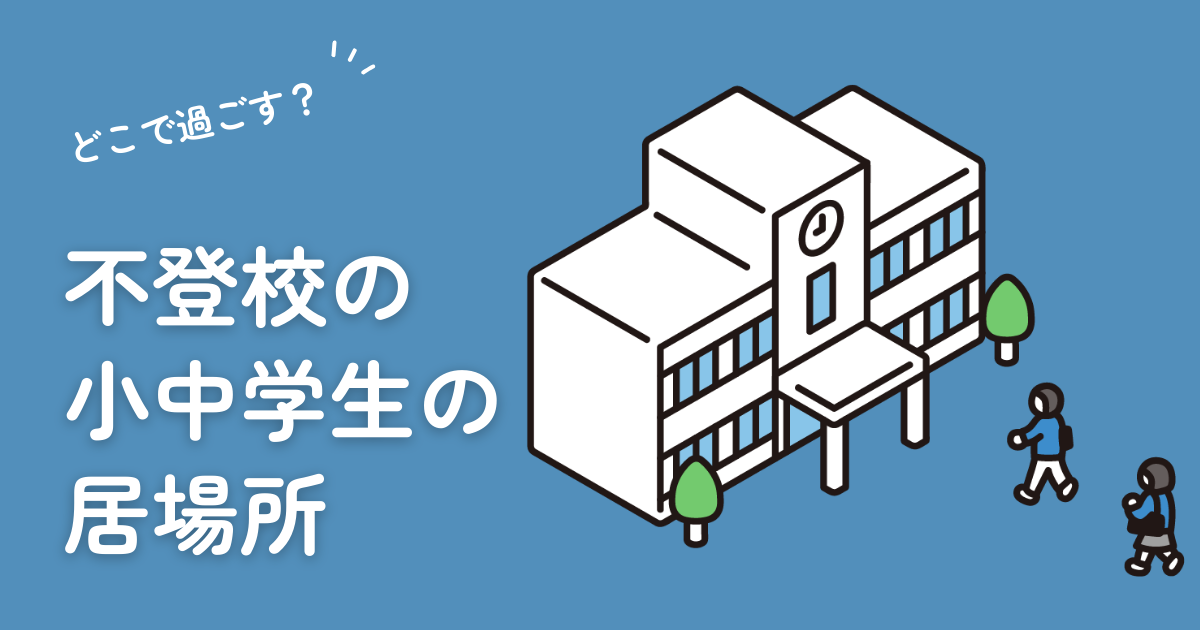
コメント